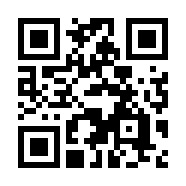「トラツグミの生態は?どんな鳥なの?」
トラツグミ(スズメ目ヒタキ科)は、低地から山地のよく茂った林にすみ、繁殖期になると夜にさえずります。
日本全国で繁殖しますが、林の中なので、あまり姿が見られません。
トラツグミの生態まとめ表

| トラツグミの特徴や基本情報 | |
| 分類 | 動物界/脊索動物門/脊椎動物亜門/鳥綱/スズメ目/ヒタキ科/トラツグミ属 |
| 特徴 |
|
| 会える季節 | 1年中見られ、日本全国で繁殖する また北の地方のものは冬に暖地へ移動する(北海道では夏鳥) |
| 会える場所 |
|
| 会える地域 | 日本全国(奄美大島では亜種オオトラツグミが、現在は確認されていないが西表島には亜種コトラツグミが生息していると考えられている) 世界分布 |
| 名前 |
|
| 名前の由来 |
|
| サイズ/体重 | 29.5cm/150g |
| 食べ物 | ミミズや昆虫、木の実など 狩りのスタイル
|

| トラツグミの生態や子育てについて | |
| 鳴き声 | さえずり 「ヒー、ヒョー」とさ口笛のような声でさえずり、夜に鳴く(曇りの日や雨の日には日中でもさえずりを聞く事がある) 地鳴き 普段は「ガッ」と鳴く 【トラツグミの鳴き声試聴サイト:さえずりナビ(外部サイト)】 |
| 寿命 | 情報がなく、不明 |
| オスとメス | 同じ見た目で、外見からの判断は難しい |
| 歩き方 | 足を交互に出して歩く |
| 似た鳥 | |
| 性格 | 繁殖期は林の中で行い、人目につかないようにしているが、秋冬には比較的近くで観察できる機会が多く、人に対する警戒心は高くない |
| 行動 |
|
| 子育て |
|
トラツグミの補足情報
秋冬のトラツグミ

トラツグミは、秋冬には開けた場所で採食している事も多く、場所の特定ができれば、かなり近づく事ができ観察しやすい鳥です。
トラツグミと会うには、秋冬に広めの林がある公園に行ってみるのがおすすめです。
昔は妖怪だった?
トラツグミは独特の鳴き声と夜に鳴く習性、さらに姿が見えない事から、万葉集の和歌では「悲しさや寂しさ」の象徴として扱われてきました。
その後、源頼政が宮中で捕らえた怪物は、頭はサル、体はタヌキ、尾はヘビ、手足はトラのようで、その声は「ぬえ」のようであると記された事から、名の無いその怪物は、のちに「ぬえ」と呼ばれるようになり、「ぬえ」=「怪物」という図式ができあがったと言われています。
そうして、妖怪ぬえが誕生し、ぬえの鳴き声を持つトラツグミは妖怪になりました。
ぬえの正体がトラツグミだとわかったのは、江戸時代になってからです。