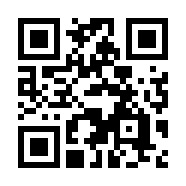「カヤクグリってどんな鳥?」
カヤクグリ(茅潜)は、スズメ目イワヒバリ科に分類される一年中日本で見られる留鳥で、日本特産種です。
高山で繁殖し、秋冬は平地でも見られます。
高山を主な生息場所にしているため、人に関わる機会が少なく、警戒心が低い傾向があります。
カヤクグリってどんな鳥?

| カヤクグリってどんな鳥? | |
| 分類 | 動物界/脊索動物門/脊椎動物亜門/鳥綱/スズメ目/イワヒバリ科/カヤクグリ属 |
| 英名 | Japanese accentor |
| 学名 | Prunella rubida 意味赤い小鳥 |
| 別名 | かやくき、おおみそさざい、やまさざい、しばもぐり、ちゃやどり |
| 生息地 | 九州以北(九州では冬鳥) 国内繁殖地 四国の剣山、本州中部以北、南千島 ■見られる月:1年中(秋冬は平地でも観察できるので特に多い(12〜2月) ▶︎繁殖地では、5月中旬頃から見られ始め、10月頃に越冬地へ移動し始める |
| 世界分布 | ロシア(南千島) |
| 生態 |
|

| カヤクグリの特徴 | |
| 特徴 |
|
| 鳴き声 | ♪「チリリチュウチイ ピイピイチリリリ」と細い声でさえずる ♪地鳴きは「チリリリ」 カヤクグリの地鳴きチリリリ |
| サイズ | 全長14cm |
| オスとメス |
|
| 子育て |
|
カヤクグリQ &A

カヤクグリの漢字は?
茅潜
「茅(かや)」ススキやイネ、アシなど茅葺きに使用する様々な植物の総称。
チガヤとも呼ばれるイネ科の多年草で、よく見かける雑草の古名。
萱潜
「萱(かや)」イネ科の植物チガヤ•ススキなどの総称。屋根をふくのに使う。
屋根表面だけの修繕は、約500万
(内訳、職人の人件費、葺き替えする際に家の周りを覆う足場代、材料費、運搬費、廃材処分代など)
カヤクグリの由来は?
和名カヤクグリは、冬季にカヤの茂みに潜むように生活することから
【茅/萱(カヤ)はススキなどの総称】
平安時代から「かやくき」という名前で知られていて、
室町時代には「かやくぐり」と呼ばれるようになった(室町時代の国語辞書「下学集」1444年出版に記載があるかと思い調べてみましたが、確認できませんでした。他の辞書?)
【外部サイト-下学集を閲覧する】
カヤクグリの特徴は?
全体的に茶色っぽい見た目をしていますが、茶色一色というわけではなく、灰色や赤茶、黒など色味は複雑です。
地上を跳ねるように歩き、細いくちばしで地上の昆虫や種子などをつまんで食べます。
人間への警戒心は低く、近くによってもあまり逃げない傾向があります。
カヤクグリのたべものは?
繁殖期には、地上に生息する昆虫を食べ、冬には種子や果実を食べています。
昆虫や種子を消化分解するために、砂を飲み込む場合もあります。
またカヤクグリの持つ細くて鋭いくちばしは、地上の昆虫や種子をつまむのに役立っています。
カヤクグリの分類は?
カヤクグリはスズメ目イワヒバリ科カヤクグリ属に分類されています。
イワヒバリ科に属する鳥類は、ヨーロッパカヤクグリと日本のカヤクグリを除けば、ヨーロッパとアジアの山岳地帯に生息しています。いずれの鳥も、冬は暖地へ移動する傾向があります。
カヤクグリの鳴き声は?
カヤクグリは高山で繁殖するため、さえずりを聴くには夏の高山に行く必要があります。
秋冬には低地に降りてくるカヤクグリは、地鳴きの「チリリ」とよく鳴くので、こちらの鳴き声の方が聴き馴染みがあるでしょう。
カヤクグリの地鳴きチリリリ
カヤクグリの観察記録

近場でもカヤクグリに会うには、秋冬の低地へ移動してきた時がいいと言うことで、11月にお山に行ってカヤクグリに会いに行ってきました!
カヤクグリは、ウグイスやミソサザイが好きそうな笹藪や茂みから地上に出てきて採食し、驚くと茂みに隠れて、またしばらくすると出てくるのを繰り返していました。
人への警戒心が低いのかジッとしていると、カヤクグリの方からこちらへ近づいてくることも多く
スマホでも撮影できてしまうんじゃないかってくらいの距離で、のんびり採食していました。
また車道の脇の落ち葉が積もった場所でも採食活動していたので…
秋冬のお山だったら、もしかしたらどこにでもいるのかな?
と思ってしまうほど、お山での遭遇率は高い鳥さんでした。