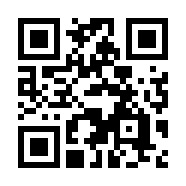「センダイムシクイの生態は?どんな鳥なの?」
センダイムシクイ(スズメ目ムシクイ科)は、夏鳥として日本の低山にやってくる渡り鳥です。
林の上部を好み、活発に移動して、木の葉の裏にいる昆虫などを捕食します。
fa-assistive-listening-systems
センダイムシクイの鳴き声
センダイムシクイの生態まとめ表

| センダイムシクイの特徴や基本情報 |
| 分類 | 動物界/脊索動物門/脊椎動物亜門/鳥綱/スズメ目/ムシクイ科/ムシクイ属 |
| 特徴 | - 体の上面はオリーブ緑色で、白い眉斑の上は暗色で、灰緑色の頭央線がある(頭央線:頭の真ん中を走る羽模様)
- 大雨覆先端はわずかに白い
- 下面は汚白色で、脇は緑褐色を帯びる
- 上嘴は黒褐色で、下嘴はオレンジ色。足は褐色
|
| 会える季節 | 夏鳥として飛来する 4月中〜下旬から5月上旬頃に飛来し、10月頃に越冬地へ旅立つ |
| 会える場所 | 低山の落葉広葉樹林で見られ、小規模な林では見られない |
| 会える地域 | 九州以北(九州では少ない) 世界分布
中華人民共和国北東部•日本•ロシア南東部•朝鮮半島で繁殖し、冬季になるとマレー半島•ジャワ島•スマトラ島などの東南アジアで越冬する |
| 名前 | - 漢字:仙台虫喰
- 英語名:Eastern crowned-warbler
- 学名:Phylloscopus coronatus
|
| 名前の由来 | - 日本語名「センダイムシクイ」は「鳴き声がチヨチヨビィーと聞こえる」から「千代虫喰(ちよむしくい)」と呼ばれていたのが、転じて「千代(センダイ)」となった事から。「ムシクイ」は昆虫食の生態から
- 英語名「Eastern」は「東の地方の」を、「crowned」は「頭の中央線を冠に見立てた」から、「warbler」は「さえずる鳥」という意味
- 学名の「Phylloscopus」は「葉の観察者」を、「coronatus」は「冠のある」を意味する
|
| サイズ/体重 | 12cm/7〜12g |
| 食べ物 | 昆虫、クモなど 狩りのスタイル - 木の上で獲物を探す事が多く、枝から枝へ頻繁に移動する
- 枝から見上げるように葉の裏を探し、見つけた昆虫に飛びついて捕食する
|
![枝からのぞくセンダイムシクイ]()
| センダイムシクイの生態や子育てについて |
| 鳴き声 | さえずり
「チヨチヨビィー」「チチヨチチヨジー」「チュインチュインチュイン」などとさえずる。またさえずりは「焼酎一杯、グィー」と聞きなしされる地鳴き
普段は「フイッ、フイッ」と鳴く 【センダイムシクイの鳴き声試聴サイト:さえずりナビ(外部サイト)】 |
| 寿命 | 情報がなく、不明 |
| オスとメス | 同じ見た目で、外見からは判断が難しい |
| 歩き方 | ピョンピョンと跳ねるように歩く |
| 似た鳥 | 他のムシクイ科の鳥やウグイス科の鳥と姿が似ている 識別の多くは、鳴き声の聞き分けが重要 |
| 性格 | 木の上にいるが、林道付近で活動する事も多く、警戒心が強いながらも、ウグイスに比べれば、多少は観察しやすい |
| 行動 | 生活スタイル- 行動のほとんどを林の中で行い、開けた場所には出てこない
- カラ類やメジロなどと混群を作って、一緒に行動する
単独〜ペアで行動 - 群れは形成せず、単独かペアで生活するので、群れていれば雛を連れた家族の可能性が高い
|
| 子育て | - 5〜6月頃に、草の根元や崖の窪みなどに、枯葉や樹皮•コケなどを使った横に出入り口のある球形の巣を作り、4〜6個の卵を産む
- 卵は約13日で孵化し、オスとメスで温める
- 孵化した雛は約14日で巣立つ
- またツツドリに托卵される事がある
|
参考文献
「フィールドガイド日本の野鳥/高野伸二 著」「
野鳥観察ハンディ図鑑 山野の鳥/安西英明 解説/谷口高司 絵」「
バードリサーチニュース2005年4月号」「
実用•現代用語和英辞典」「
センダイムシクイ」