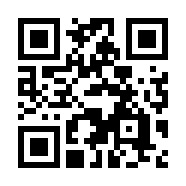「ハギマシコってどんな鳥?」
ハギマシコ(萩猿子)は、スズメ目アトリ科に分類される冬鳥です。
特徴的な腹部の斑紋が萩の花のように見えることから、ハギマシコと名付けられたと言われています。
星4の珍しさ

ハギマシコってどんな鳥?

| ハギマシコってどんな鳥? | |
| 分類 | 動物界/脊索動物門/脊椎動物亜門/鳥綱/スズメ目/アトリ科/ハギマシコ属 |
| 英名 | Asian Rosy Finch |
| 学名 | Leucosticte arctoa 意味北極の白い斑点のある鳥 |
| 別名 | いわすずめ、くろはぎ、くろあとり、はぎすずめ、はぎしとと、やぶすずめなど地域によって別名があり、古くから身近な鳥だったと考えられる |
| 生息地 | 北日本に飛来するが、他の地域でも少数の記録がある ■見られる月:12〜4月 |
| 世界分布 | 繁殖地 モンゴルと旧北区(東アジアの大部分)の東 越冬地 満州、韓国、サハリン、日本 |
| 生態 |
|

| ハギマシコの特徴 | |
| 特徴 |
|
| 鳴き声 | ♪「ヂュッ」「ヂュー」と濁った声で鳴く ♪他にもスズメに似ている声で「チィッ」「チュッ」「チューチュー」と鳴く ♪群れが飛び立つときや飛翔中によく鳴く ハギマシコの鳴き声 |
| サイズ | 全長16cm |
| オスとメス |
|
| 子育て |
|
ハギマシコの姿
ハギマシコのオスとメス

ハギマシコのオスは、目に見えて鮮やかな色をしていますが、
天気が悪かったり、光が当たってなかったりすると、オスもメスも黒っぽく見えます。
![]()
ハギマシコの個体差

ハギマシコの食事
ヤシャブシの実をつつくハギマシコ

ハギマシコは、群れになって地上で採食する様子がよく見られますが、
今回はヤシャブシの木にとまり、実をつつく様子も観察できました。
群れで地上採食するハギマシコ

ハギマシコは、群れで地上に降りて採食することも多く、植物の種子などを食べています。
ハギマシコがやってくる有名な場所では、文鳥のエサなどがまかれていることが多く、
今回の記事作成にあたって、2か所でハギマシコに会えましたが、1ヶ所では文鳥のエサがまかれていたようでした。
その為、ハギマシコのやってくる頻度も午前中は30分に一度やって来るくらいでした。(餌付けの賛否については、この記事では割愛いたします)
ハギマシコの観察記録

おさんぽ鳥見編集部が出会ったハギマシコは、登山道の舗装された道で、群れで採食していました。
曇り空ということもあり、全体的に黒っぽく見えましたが、双眼鏡やカメラで確認してみると、その姿はハギマシコ!
最初はカワラヒワが群れで採食しているのかと思いましたが、
山にカワラヒワはあまりないので、アトリあたりかなと思ってました。
その後、ハギマシコがやってくるというポイントで待っていると、
空から鳴きながら小鳥の群れが!
鳴きながら数回往復したのち、近くの木にとまり、しばらく様子をうかがったり、木の実を突いたり…
1羽2羽が地面に近づいてきて、降りて採食を始めると
それに続いて群れが地面で忙しなく採食を始めました。
物音を立てると、すぐに飛び立ってしまうので、観察の際は静かにします。
すると、採食に夢中のハギマシコは、どんどんこちら側に近づいてきて…
限界まで近づくと、ハッと我に帰ったように飛び去って
どこかに行ったり、また木にとまったりしていました。
木にとまって、しばらく様子を見ている感じの時は、
再び地上に降りて採食してくれたので、飛来してきてくれれば、会える頻度は高そうでした。
天気が悪い時でも午前中はよく採食に来て、午後以降は日によってまちまちで群れがやってこない時間が長くなっていたので、観察するなら午前中が良い感じでした。