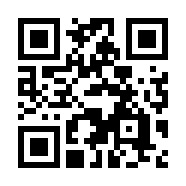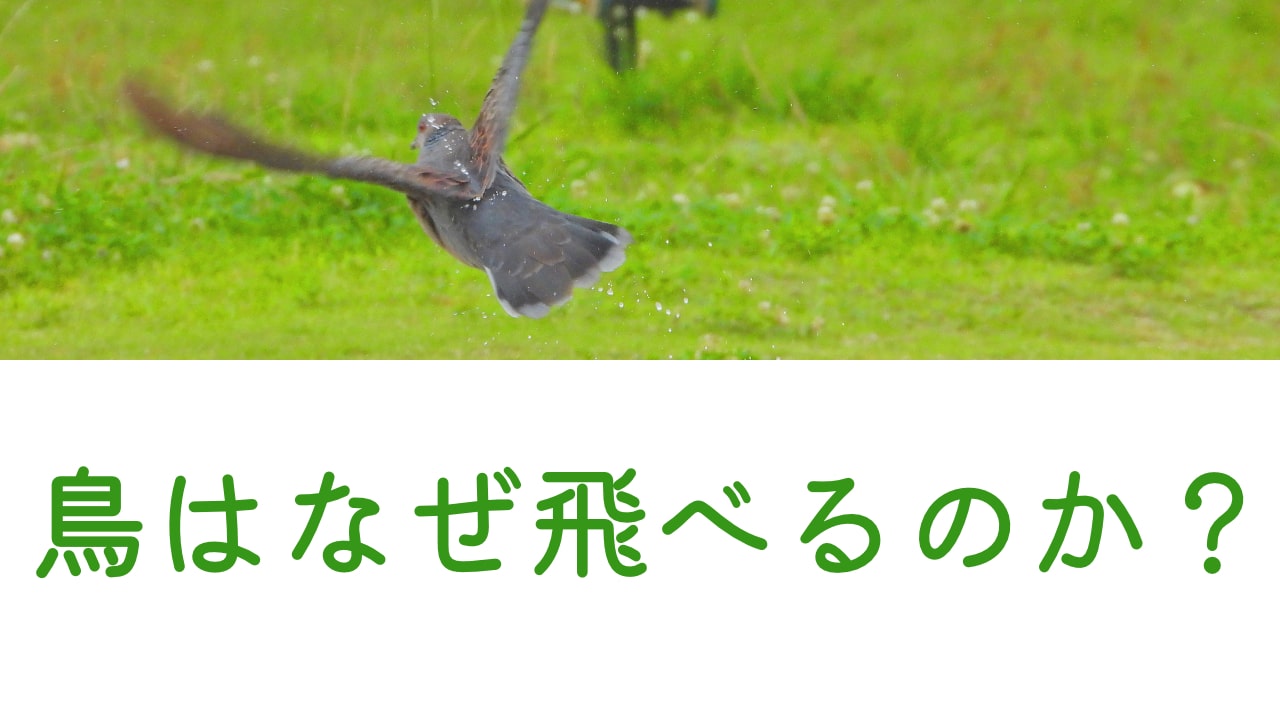
「鳥はどうして飛ぶの?なんで飛べるの?」
鳥が飛ぶ理由は、鳥として生きる為です。鳥は生きる為に飛び、体の構造を飛べるように適応させてきました。
鳥が飛ぶ理由
「鳥はなぜ飛ぶのでしょうか?」
![]()
鳥の飛翔は「目的を持って空中を移動する事」と言えます。
| 鳥が飛ぶメリットは? |
| 行動圏の拡大 |
| 食べ物探しのしやすさ |
| 危険を回避しやすくなる |
| 環境からすぐに逃げれる |
| 群れを作りやすい |
| 季節に合わせて移動できる |
鳥はなぜ飛べるのか?
「鳥はなぜ飛べるのか?」
![]()
もちろん、翼があるのも鳥が飛べる理由の一つです。
ですが、もし人間に翼があったとしても、鳥みたいには飛べないんです…
鳥の翼の役割
鳥は羽ばたく事で推進力を得て、飛んでいます。
飛ぶ為に重要な翼には、初列風切羽と次列風切羽の2種類の羽があり、初列風切羽が推進力を生み出します。
初列風切羽
翼を打ち下ろすと、初列風切羽がひねられ、後方に空気を押し、推進力を生み出します。
これはプロペラが回転して推進力を生み出す仕組みと同じです。
次列風切羽
また次列風切羽は、体を上に押し上げる揚力を生み出しています。
飛ぶ為の体の構造
飛ぶ為に、鳥の体の構造は、人間とは大きく異なる部分がいくつかあります▼
飛ぶ為の体の構造
- 骨を軽くして、鳥だけに見られる骨がある
- 視力は、人間の5?8倍以上
- 気嚢と肺臓で、筋肉に効率よく常に新鮮な酸素を供給する
- 心臓は高速度で血液を循環させる
- 総排泄孔で屎尿を同時に排泄する
- 飛び立つ前にフンをし、頻度も高い
気嚢(きのう)
一方通行の循環システムで、ガス交換、燃料輸送、熱の排出を効率よく行う器官です。
気嚢の凄さ
気嚢は9つあり、すべてがつながっていて、肺臓に結びついています。
気嚢は吸い込んだ空気を蓄え、絶え間なく円滑に肺臓に送り込む機能を持っていて、気嚢があるおかげで、鳥は常に新鮮な空気を吸えるようになっています。
高い所も飛べる!
また気嚢のおかげで、鳥は空気が薄い高い空を飛んでも平気でいられます。
ただ高所を飛べる鳥は、大型の物に限られていて、小鳥などは高くても1,000mほどが限界のようです。
人間にも翼があれば飛べるの?
「人間にも翼があれば飛べるの?」
上記の「鳥の飛ぶ為の体の構造」を見ていただければ、人間に翼だけあっても飛ぶのは難しそうです…
![]()
人間が飛べない理由
鳥の飛翔を支える胸筋は、平均で体重の約20%あるのを知っているでしょうか?
この胸筋、人間では体重の1%しかありません。いくら筋トレしようと、鳥の胸筋には敵いません。
なので、人間がいくら胸筋を鍛えても、飛ぶことはできないんです…
![]()
人間の重さで飛ぶには、巨大な翼が必要になります。
ですが、翼が巨大になればなるほど必要な力も上がり、翼の付け根にも強い力がかかり、強度的にも羽ばたく事ができません…
飛べる鳥の限界
鳥が飛ぶには「翼、飛ぶ力、体の構造」など、飛ぶ為の適応が必要な事がわかりました。
人間に翼があっても飛べないのは、人間が重すぎるのも理由の一つでした。
![]()
理論上では、鳥は体重16kgまででないと、飛ぶ事ができないようです。
そして、飛ばなくなった鳥は、体重が増加する傾向があり、ダチョウの体重は約120kg。
泳げるが、飛べない大型のペンギンの体重は約30kgで、飛ぶ鳥に比べてかなり重くなっているのがわかります。
鳥以外の飛ぶ動物
| 鳥以外の飛ぶ動物と飛び方 | |
| 手を使って飛ぶ | 鳥、コウモリ、ムササビ、モモンガ類、ヒヨケザル |
| あばら骨を広げて飛ぶ | トビトカゲ、ヘビの1種 |
| 翅で飛ぶ | 昆虫類 |
| 脚力で飛ぶ | ノミ、バッタ、カンガルーネズミなど |
| 細い糸で飛ぶ | クモの子 |
| 水を噴射し飛ぶ | オオトビイカ |
鳥は飛びたくない?
大陸から離れた島に暮らす鳥の多くは、飛ぶのをやめてしまう傾向があります。
- 食べ物がたくさんある
- 天敵がいない
- 移動する必要がない
など、色々な条件に適応した結果が作用して、鳥は飛ばなくなります。
飛ばなくなった鳥の一例
飛ばなくなった鳥には、ガラパゴス諸島のガラパゴスコバネウ、沖縄のヤンバルクイナ、ニュージランドのカカポなどがいます。
![]()
ですが、飛ばなくなった鳥たちは、人間の進出により天敵が持ち込まれたり食用にされたり、悲惨な運命を辿ってしまったものも多くいます。
鳥の飛行チャンピオン
| 鳥の飛行チャンピオン | |
| 瞬間速度 | ハヤブサは獲物を狙い急降下する時、時速300kmで飛びます |
| 速度 | 北極圏で繁殖するケワタガモは、観察された中で最も早い時速76kmで飛び続けた記録があります |
| 1日の移動距離 | 北極圏で繁殖し、北アメリカで冬越しするハクガンは、1日に2,000km飛んで移動していました |
| 総移動距離 | キョクアジサシは繁殖地の北極圏と越冬地の南極海を往復していて、毎年地球をほぼ1周する距離と同じ3万?4万kmを飛んでいました(1日で飛ぶわけではなく、何日もかけて途中休憩を挟みながら移動します) |
| 標高 | キバシガラスはエベレストの標高8,848mで観察された事もあります |
鳥の飛べない時期
![]()
鳥の羽は活動していれば汚れてしまうので、鳥は羽毛が生え替わる換羽を行います。
多くの小鳥の場合
スズメ目の鳥では、年に1回、全身の羽毛が換羽し、繁殖が終わった夏から秋にかけて行われます。
換羽は1度に一気に抜けるわけではなく、部分ごとに順番に抜けていきます。
部分的に抜ける事で、換羽が終わるのは2ヶ月くらいかかってしまいますが、飛翔能力を維持したまま行えます。
飛べなくなる換羽
水鳥のガンやカモの仲間は渡りの前に風切羽が一気に抜けて、まったく飛べなくなる換羽を行います。
この時期は、無防備になってしまいますが、換羽が早く済み、渡りの前に備えられるんです。
飛ぶ鳥を参考に発明!
飛ぶ鳥を研究する事で、さまざまな飛ぶ道具が発明されました。
最も有名なものは「飛行機」です。
他にも、19世紀イギリスの物理学者のジョージケリーは、鳥が羽ばたかなくても飛べる事を発見し、グライダーを考案し、日本人の二宮忠八も、カラスが羽ばたかずに飛ぶ姿からヒントを得て、カラス型模型飛行機を作りました。
参考文献
「鳥の雑学がよ?くわかる本/柴田佳秀(著)」「図解雑学鳥のおもしろ行動学/柴田敏隆(著)」「鳥の骨探/安部みき子(著),、松岡廣繁(著)」